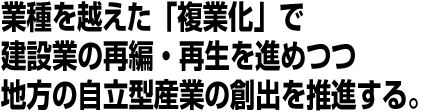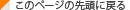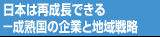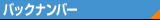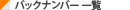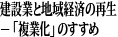
米田 雅子(慶応義塾大学理工学部教授)
地域社会・経済に果たしてきた建設業のこれまでの役割
建設業の本来的な役割は、その時代や地域に必要な社会基盤、社会資本というものをしっかりとつくり、適切な維持管理を行い、現在そして50年後、100年後も社会を支えていくことだ。つまりストック効果を生み出すことだ。
ところが先に見たように80年代の後半から90年代にかけては、雇用としての公共事業、内需拡大策としての公共事業(=フロー効果)が重視されすぎて、建設業本来の役割が見失われた側面があるのではないかと思う。
これまでの日本の歩みを振り返れば、高度経済成長期には、「国土の均衡ある発展」を図るために、地方に先行的に道路や空港などの社会基盤をつくり、工場を誘致して産業の分散立地を図るという政策が展開されてきた。
社会資本を整備することで、地方に新たな産業をもたらし、農林水産業の生産性や付加価値性を高め、地方の自立や活性化を促したわけである。これにより、都市の過密と地方の過疎という高度経済成長の弊害が是正され、全国的に格差の少ない1億総中流の社会が実現した。この「国土の均衡ある発展」という考え方は、その後も「三全総」や「ふるさと創生論」に受け継がれている。
このように建設業は地方への社会資本整備を通じて、地域産業を活性化する役割を担い、今もそれは変わらない。一方で公共事業の現場は、地域の雇用の現場ともなる。このため建設産業は本来の社会基盤整備に加えて、地方の雇用の受け皿という役割も担った。その役割が大きくクローズアップされたのが、80年代後半から90年代にかけての膨張期と言うわけである。
時代は変化し、「雇用の受け皿」としての建設産業の役割は終焉を迎えつつある。今、縮小を迫られているのは「必要な社会基盤」ではなく、「雇用のための公共事業」である。
建設業は社会基盤整備という、本来の有るべき姿への回帰を進めるべきである。そして地方は、公共事業や建設業だけに依存しない地域の雇用創出策を考える必要がある。これまで整備してきた社会基盤を利用して、各地域が自立型の産業を生み出していく。苦しいことではあるが、地方はそこに取り組んでいかなければならない。